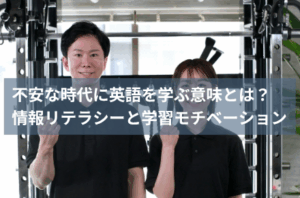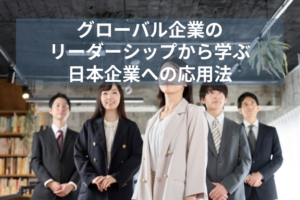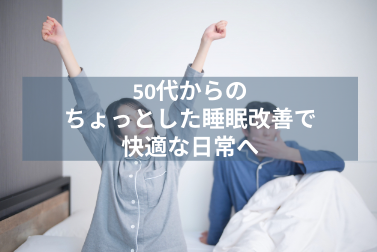「日本人はミーティングでは静かだからねー」
あるグローバル企業に転職して間もなかった頃、同僚にこう言われたことがあります。自分としては転職直後ということもあり、職場の考え方を理解するために、相手の主張を受け止めつつ、場の空気を読み、発言のタイミングをうかがっていたつもりでした。しかし、その沈黙は「話し合いに積極的に参加していない」と受け取られていたのです。
日本人にとって「空気を読む」という行為は、相手を思いやり、調和を大切にするためのコミュニケーション手段です。しかし、グローバルな職場では、これが逆に誤解を招くこともあります。今回は、この“空気を読む力”がなぜ誤解されるのか、そしてどうすればその力をグローバルな環境で活かせるのかを考えてみたいと思います。
空気を読む=日本人の強み?
日本では、「言わなくても伝わる」「相手の気持ちを察する」といった非言語のやり取りが当たり前のように行われます。これはハイコンテクスト文化と呼ばれ、言葉以外の要素(表情、沈黙、文脈など)から意味を読み取る文化です。
この文化の中で育った私たちは、言葉にしない「間」や「気配」を敏感に察知する能力に長けています。たとえば、会議中に誰かが発言をためらっていると気づいたとき、あえて話を振ったり、空気を和らげたりする行動は、日本人ならではの配慮といえるでしょう。
この“空気を読む力”は、チーム内の調整や、対立の火種を未然に防ぐといった面で、大きな武器になります。
グローバル職場では通じにくい理由
一方、ローコンテクスト文化圏では、明確な言語化が重視されます。「言わない=存在しない」と解釈されることすらあります。沈黙は合意ではなく、疑問や反対意見の欠如と見なされてしまうのです。
そのため、日本人特有の「発言を控える」「場の空気を読む」といった行動は、「消極的」「意見がない」と誤解される可能性があります。国際的な職場では、自分の考えや立場を、たとえ完璧でなくても言葉にして伝えることが求められます。
空気を読む力をどう活かすか?
では、この“空気を読む力”をグローバルな場でどのように活かせばよいのでしょうか。
まず重要なのは、「察する力」と「伝える力」をセットで使うことです。相手の意図や気持ちを読み取るだけでなく、それを自分なりに解釈し、簡潔な言葉で返すことが大切です。
たとえば、「I understand your concern. From my perspective…(ご懸念は理解できます。私の立場では〜)」のように、相手の気持ちに寄り添いつつ、自分の意見も明示することが、誤解を避ける第一歩です。
また、会議での沈黙には、「I’m processing my thoughts. I’ll share my idea in a moment.(今、考えを整理しています。少ししたら意見を述べます)」などと一言添えるだけで、意欲的な姿勢が伝わります。
体験談:空気を読む力がチームの潤滑油に
私が所属しているグローバルチームには、それぞれの意見を聞きながらも、自分の意見をはっきり言うメンバーが多数います。ときには彼らの主張がぶつかり合うこともあり、前に進まないことがあります。
そこで私は、両者の言葉や表情の変化を注意深く観察し、一方的に否定するのではなく、それぞれの意見の良い点と懸念点を整理して伝え、彼らが気づかない別の視点を提示しました。特に慣れるまでは、自分の意見は会議の後半、ある程度みんなの意見が出そろったタイミングで伝えるようにしていました。
お互いの性格なども分かってくると、自然と空気を読めるようになり、ミーティングでもより自然に意見を伝えられるようになっていきました。
まとめ:日本人の繊細さは世界で通用する
“空気を読む力”は、確かに日本特有の文化的資質かもしれません。しかしそれは、相手への配慮や共感を大切にするという、国際社会でも評価されるソフトスキルです。
大切なのは、読み取った空気を「翻訳」し、自分の言葉で共有する勇気です。日本人の繊細さを、グローバルな職場の中で「強み」として活かすために、まずは一言、日本語、英語関係なく自分の意見を言ってみることから始めてみませんか?
ブリッジ-e1724390527855.png)